- 1970.01.01
- 未分類
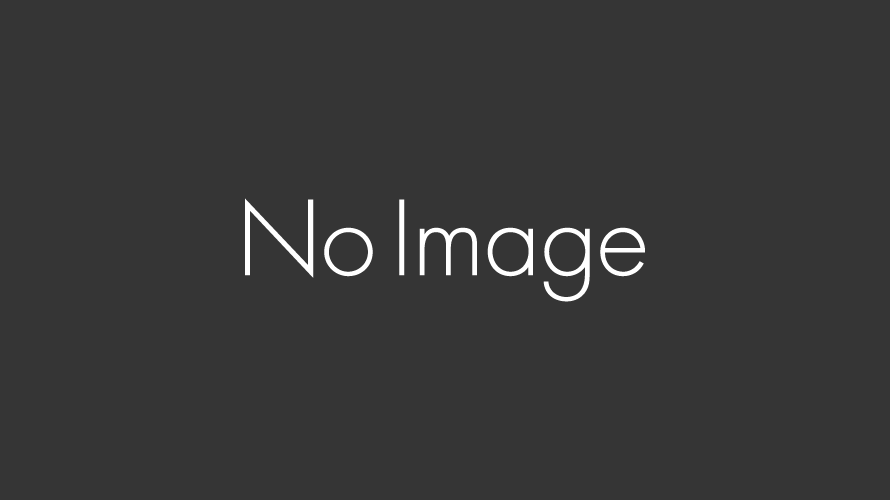
梅雨があけたと思ったらいきなりの猛暑…。まだ7月なのにすでにバテバテの状態です。しかし、このうだるような暑さに負けず、今年の夏も海に山にとイベントも盛りだくさん。グラビティでも、夏のイベントに向けたグッズの作成でただ今大忙しです。
さて今回はそんな夏の印刷の中から、定番だけど意外と利用されない「暑中見舞い」についてご案内したいと思います。暑中見舞いのルールや、ただの挨拶状で終わらせない、もらって嬉しいちょっとしたアイデアまでまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
暑中見舞いを送る時期
暑中見舞いは梅雨が明ける7月上旬から夏の土用の期間、立秋前まで8月5日〜6日くらいまでを目安に送ることが一般的となっております。立秋(8月7日頃)を過ぎると、まだ暑さのピークは続いても暦の上では残暑扱いとなり、暑中見舞いを出すタイミングとしては遅くなってしまいます。
画像(暑中見舞い送る時期棒グラフ)
暑中見舞いは夏の厳しい暑さに対しての安否の伺いが本来の意味となるので、梅雨があけ、本格的な夏の暑さが到来したくらいの時期に出すことが望ましいです。
また、もしこの時期を逃してしまった場合でも、「残暑見舞い」に変更して送ることができれば問題ありません。
暑中見舞いの書き方
それでは次に暑中見舞いの書き方についてご案内します。
暑中見舞いは大きく4つの構成で作られています。
画像(暑中見舞いの構成)
1.冒頭の挨拶
まず、冒頭の挨拶を大きく掲載します。一般的には「暑中お見舞い申し上げます」といった定型の挨拶が入ります。
2.時候の挨拶や先方の安否を気づかう言葉
「暑い日が続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか」
3.自分の仕事やプライベートのことなど、相手に伝えたい近況の報告
4.結びの挨拶
先方への気遣い、または感謝の言葉などを用いて、文章を締めくくります。
5.日付
最後に日付を入れて完了です。日にちまでは記入せず、年月のみ(平成○年○月)の場合や、「平成○年 盛夏」とすることが多いです。ちなみに残暑見舞いの場合は「平成○年 晩夏」とします。
暑中見舞いのアイデアはがき
たかが暑中見舞い、されど暑中見舞いです。紙の質感や手書きならではの温もりは、気持ちの伝わるアイテムとして見直されはじめ、暑中見舞いのような日本的なアナログの習慣が、いま密かなブームとなっています。
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事

販促に強い。ノベルティにステッカーが選ばれる理由 2017.05.16